モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす! 0〜3歳までの実践版
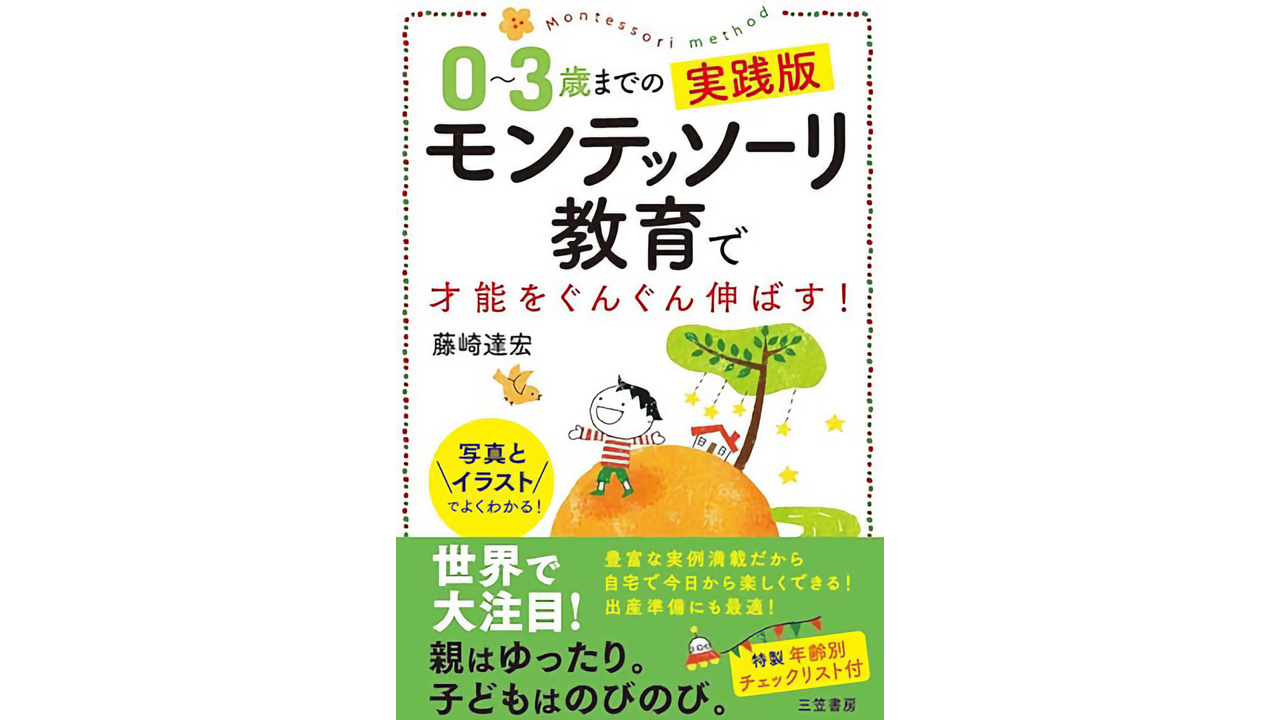
モンテッソーリ教育
「一人で生きていく力(成長のサイクル)」を自分で獲得できるように、親は見守り、手伝ってあげる。 環境を整え、やり方さえ教えれば、子どもは何でも自分でできる。子どもの成長は、環境がすべて。 何を「いつ」与えるのか、そのタイミングを大切にする「適時教育」。
成長のチェックリスト
「環境は整っているか、働きかけているか」を見直すために使用する。 次の段階へのステップは、それ以前の段階をいかに充実して経験してきたかにかかっている。 時が来れば、子どもは自分の判断で次のステップへと進む。
発達の四段階
0〜3歳では、覚える努力や意思の力なしに、すべてを素早くとらえ、永久的なものとして記憶する力を持っている(無意識的記憶)。 この力を利用して、人生を生き抜くための生活習慣を身につける。
成長のサイクル
新たな興味関心を自分で探し、挑戦し、成功することで、成長のサイクルがまわる。
- 置かれた環境を興味関心を持って散策
- 活動を自分で選択
- 人生を切り開いていくには、自分で決めていく習慣がもっとも必要
- 活動を繰り返す
- 上達することで満足感と達成感
- 一連のプロセスにより「自分でできた」という自己肯定感の芽が育つ
- 小さな成功体験の積み重ねで「挑戦する心」が湧いてくる
間違った成長サイクル
「xxしてあげよう」という思いが、わが子の成長を一番邪魔する。 自分で選んで最後までするからこそ「自分を信じる=自身」が生まれる。 どんなに上手にできても、人にやってもらったのであれば「他信」しか生まれない。
イタズラ
成長の過程で、そこ子にしかわからない「神様からの宿題(生きていくための練習)」を真剣にこなしている最中。
0〜1歳の子どもの育て方
秩序の敏感期
子どもは秩序(最初はこうで、次はこう、最後はこうなるはずだ)を手がかりにして、世の中を理解していく。 キーワードは「いつもと同じ」。将来自分で活動するときに「段取り」を組めるようになる。
赤ちゃんをお迎えする4つのコーナー
「いつもと同じ場所で、いつもと同じ順番で」がポイント。
- 授乳コーナー
- おむつ交換のコーナー
- 運動するコーナー
- 寝るコーナー
道具
- トッポンチーノ
- イタリア風お布団。秩序の敏感期を味方につけた逸品
- モビール
- 生まれてすぐに、しっかり見る(物に焦点を合わせる)練習を始める
- トラッカー
- どの子にも大人気
0歳児の棚
棚はとても大切な存在。 自分で選択できるように、一番下の段に教具を「2個」並べておく。 子どもの目線が集中する「ホットコーナー」を意識する。
言語の敏感期
話しかける3つのポイント
- 口もとを大きく動かし、よく見せながら発語する
- ゆっくり、はっきりを心がける
- 普段よりも高めの声で
出会いは「実物」から
抽象についていけない。 人が指差す先にある物を見ること(共同注意)ができるようになる。
言語の三段階
- 見たことがある
- 本物を見せ、名前を聞かせる
- アウトプットを求めない
- 見たことがあり名前を知っているが言えない
- 「りんごどれ?」、「りんごちょうだい」と聞く
- りんごを指差したり、手渡ししてくれる
- 見たことがあり名前を知っていて言える言葉
- 「これなーに?」と聞く
1〜2歳の子どもの育ち方
運動の敏感期
人間は、立ち上がることで手が自由になり、手を使うことで脳が発達し、直立することで咽頭が下がり、言語が話せるようになった。 わが子の頭を良くしたいのであれば、手指(突出した脳)をたくさん使わせる。
歩くために歩く
この年代では歩くことが第一優先。 近所の公園に自分の足で歩いて行き、階段をのぼったりおりたり、砂場で心ゆくまで遊ぶことが、何よりも大切。 彼らのペースで、心ゆくまで歩くことにつき合う。 親がしてしまう最悪の選択は、「ベビーカーに縛り付ける」こと。
「教具」
教具の条件
自分でチャレンジして、自分で誤りに気づき、自分で何度もやり直して、自分で成功にたどり着く。 だからこそ「自分はできる」という自己肯定感が生まれる。
- 難しいポイントが一つだけに絞られている
- 子ども自身が自分で間違ったことに気づけるようになっている
教具の例
- 落とす、入れる、通す
- つまむ、はさむ
- ひねる、ねじる、開ける
1歳の棚・トレイ
子どもは環境がそろえば自発的に活動を始める。見やすく、取り出しやすく、お片づけがしやすい棚が不可欠。 お片づけできる子どもに育てるために一番大切なことは、大人がいつも同じところに片づけること。
「提供」
用具や教具の使い方をやって見せること。
- 子どもを誘う
- やるか、やらないかは子どもの判断に任せる
- 仕事の名前を伝える
- 活動をする場所まで運ぶ
- 子どもの利き手側に座る
伸びる教え方「3つのM」
- 見ていてね
- 待っていてね
- 待たせて最後まで見せる
- もう一度やるから見ていてね
- 一番いけないのは口での注意
何回も繰り返す = 集中現象
成長のタイミングと合っているか?そのバロメーターは「繰り返し」にある。 繰り返しやり始めたら、できる限りそっと集中を途切れないように静かに見守る。
2 〜 3歳の子どもの育ち方
できることは子どもに任せる、できないことだけ最小限に援助する。 難しい部分だけを取り出して、ゆっくりとクリアしていく(困難性の孤立)。
イヤイヤの原因3選
- 自分でやりたかった
- まず疑ってほしい原因
- 秩序が乱れた
- 子どもは大人の数十倍、場所などの秩序に敏感
- イヤイヤ期
- すぎ去るのを待つ
幼稚園・保育園の準備
- 母子分離
- 必ず迎えに来てくれるという体験の繰り返しが必要
- トイレトレーニング
- 「早く、早く」という親の思いが、排泄にたいして恐怖心を抱かせてしまう
- 「一人でできた」という自己肯定感を高めることが最終目的
- 靴・衣服の着脱
- ボタン・ファスナー
- お弁当を自分で食べる
配慮
4歳くらいまでは相手の立場になり替わって考えることが、まだできない。 自分のことが客観的に見られるようになってくると、自分以外のものや、生き物に配慮ができるようになってくる。 まわりの環境へ配慮ができたら、子ども扱いせずに、一人の人間として対等に感謝を伝える。
線上歩行
心を清め、自律を身につけることが活動の目的。「おふざけ」にならないように、真剣に取り組む姿を見せる。
叱る
わが子がこの先の人生を生きていく上で必要な価値観を真剣に伝えることが「叱る」ということ。 しつけることは、親にしかできない。
叱るときは「しっかり、その場で、短く、真剣に厳しく」叱る。 子どもは、大人の雰囲気(真剣さ、顔の厳しさ、声の大きさ)から、「これはいけないことなんだ」ということを理解する(社会的参照)。