科学的根拠で子育て
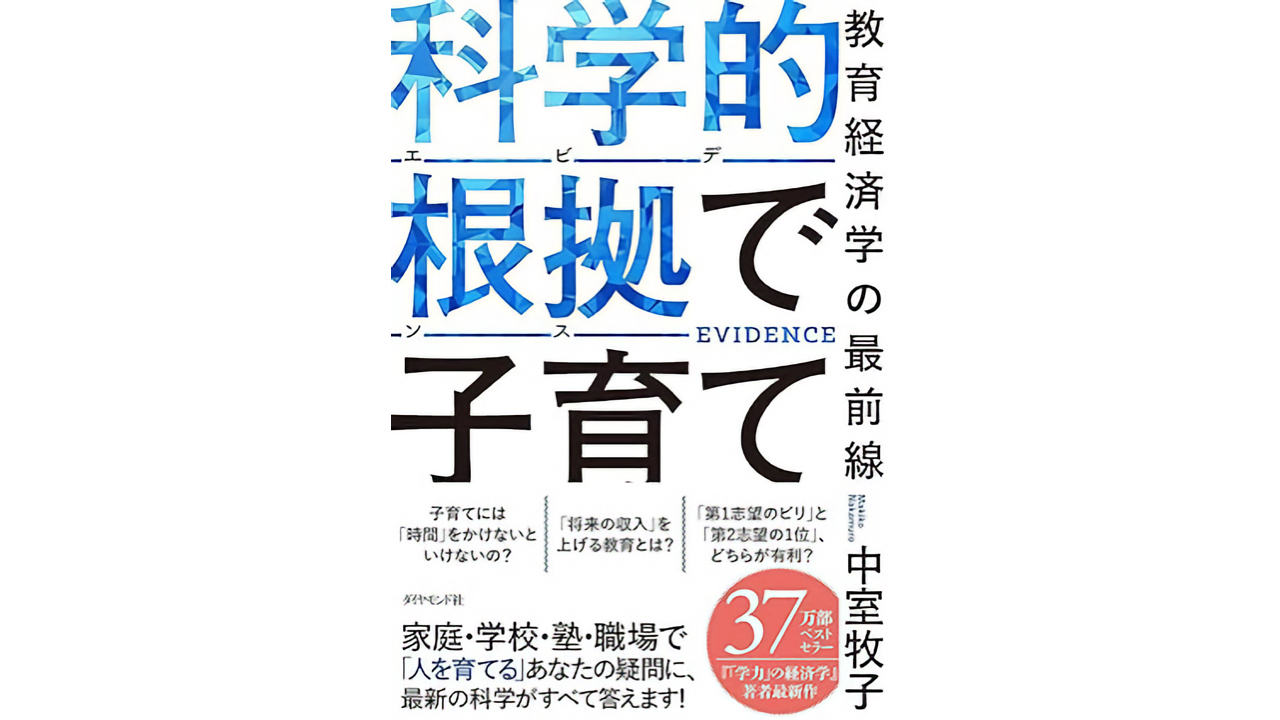
将来の収入を上げるためにすべきこと
「将来の収入」は、教育の成果の1つ。
- スポーツする
- 忍耐力、リーダーシップ、責任感、社会性などが身に付く
- スポーツで勉強はおろそかにならない
- テレビやスマホなどの「受動的な時間」が減る
- リーダーになる
- リーダーシップは、経験を積むことで習得できる「スキル」
- 親に勧められて、子どもはリーダーになる
- 非認知能力を高める
学歴と需要
社会に出ると、「勉強だけできても役に立たない」と感じることが急に多くなる。 企業採用は、コミュ力、主体性、チャレンジ精神を重視し、結婚相手は、人柄、家事・育児力、仕事への理解と協力を求める。 教育や子育ては、短期的な成果よりも長期的な成果のほうが重要。
非認知能力
非認知能力には、複利効果(「技能が技能を生む」獲得した非認知能力が、その後の教育投資の生産性を高め、認知能力を伸ばす)がある。
- 忍耐力
- 忍耐力がないと、将来に備えた行動を取れない
- 自制心
- やり抜く力
- 好奇心
- 深く学ぶことへの原動力であり、知識の定着を促す
- 「既存の概念に疑問を抱かせる」ことで掻き立てられる
- 思いやり
- 多様性の中での生活は、子どもたちの向社会性を育む
やり抜く力の伸ばし方
やり抜く力が強い人は、「成長マインドセット(努力することで自分の能力を向上させられると信じる)」を持っている。 以下のポイントを子どもに刷り込む。
- 目標設定が重要
- 目標達成には努力が必要
- 失敗や挫折を建設的に考えることが重要
- 人間の能力は生まれつきのものではなく、努力によって変えられる
幼児教育
投資収益率(利回り)
「教育が投資である」と考えたとき、大切なことは「将来いくらの利益を生むか」ということ。 その観点で幼少期の子どもに対する教育投資は「割が良い」(利回り約8%と推計)。 良質な幼児教育を提供することは、子どもたちが小学校に入学したあとに行われるさまざまな教育政策よりもはるかに費用対効果に優れている。
非認知能力と認知能力
幼少期に身に着けた非認知能力は、その後の認知能力を伸ばすのに役立つが、その逆は観察されない。 3歳時点で行われた勉強への時間投資は、ことばの発達に影響を与え、それが5歳や7歳のときに認知能力を伸ばすことを助ける。 3歳時点での認知能力は、7歳時点で25〜50%程度しか持続しないが、非認知能力は70〜90%程度が持続する。
時期
学校教育や親による教育投資は、幼少期のほうが効果的で、勉強か体験かによらず、子どもの年齢が小さいときのほうが効果が大きい。 子どもの年齢が上がれば上がるほど、親の時間投資の効果は小さくなり、子ども自身の時間投資が重要になる。 能動的な時間投資の効果は、幼少期では大きいが、年齢が上がるにつれて小さくなる。
質と影響
ある一定以上の質が担保されて初めて、子どもたちの将来の成果に良い影響を及ぼす。 幼児教育は好影響の場合と同様、悪影響であっても長期にわたって持続する。
教育方法
先生
どういった先生が非認知能力を伸ばせるのかはまだわかっていないが、子どもたちは身近にいる人たちから影響を受けて非認知能力を培っている。
本読み
親が成長マインドセットを持って接することで「質」が高まる。
- 子どもの読み書きの能力は、読み聞かせなどを通じて、鍛えて伸ばせる
- 読み聞かせの際に、子どもに本の内容を要約させたり、質問をしたりすることが大切
- 子どもが本を取って読もうとする行為を褒める
初等教育以降
勉強できる子の育て方
- 「目標」を立てる
- 自分の力でコントロールできるインプットに目標を定めるほうがうまくいく
- x「国語のテストで80点取る」 o「毎日漢字を3つ覚える」
- ある程度達成可能なインプットに対して、他人ではなく自分が、自己管理の方法について学んだ上で目標を設定すると効果的
- 自分の力でコントロールできるインプットに目標を定めるほうがうまくいく
- 「習慣化」する(習慣は第二の天性なり)
- 初期の抵抗感を和らげ、取り掛かるきっかけを作る
- ある程度繰り返させる
- 「チーム」で取り組む
- ピア効果 … 仲間や同僚がお互いの行動や生産性に影響を与え合うこと
- 社会的プレッシャー … 組織内で生じる共感、忠誠心、罪悪感など
第一志望のビリ・第二志望の一位
「鶏口となるも牛後となるなかれ」は正しい。 運良く実力より上の志望校に滑り込み合格を果たしても、学内やクラス内の順位が低ければ、長い目で見れば良い結果をもたらさない。 順位は子どもたちの「自己効力感」(自分ならきっとうまくできると、自分の可能性を信じていること)に影響を及ぼす。
優れた友人から良い影響を受けるのは、もともと学力が高い児童・生徒だけ。 自分と共通点の多い同級生のあいだでは交流が生じやすく、お互いに多くのことを学ぶ。
Tips
- 親が子どもの本当の姿を正確に把握できていない場合ほど、こどもの学力が低くなる
- 「習熟度にあった指導」を実現するアダプティブラーニングには大きな効果がある
- 適切なガイダンスの伴わない動画やデジタル教材は、子どもたちに与えるだけで害をなす
- 重要な決定とは、何をするかではなく、何をしないかを決めること