経費で落ちる領収書・レシートがぜんぶわかる本
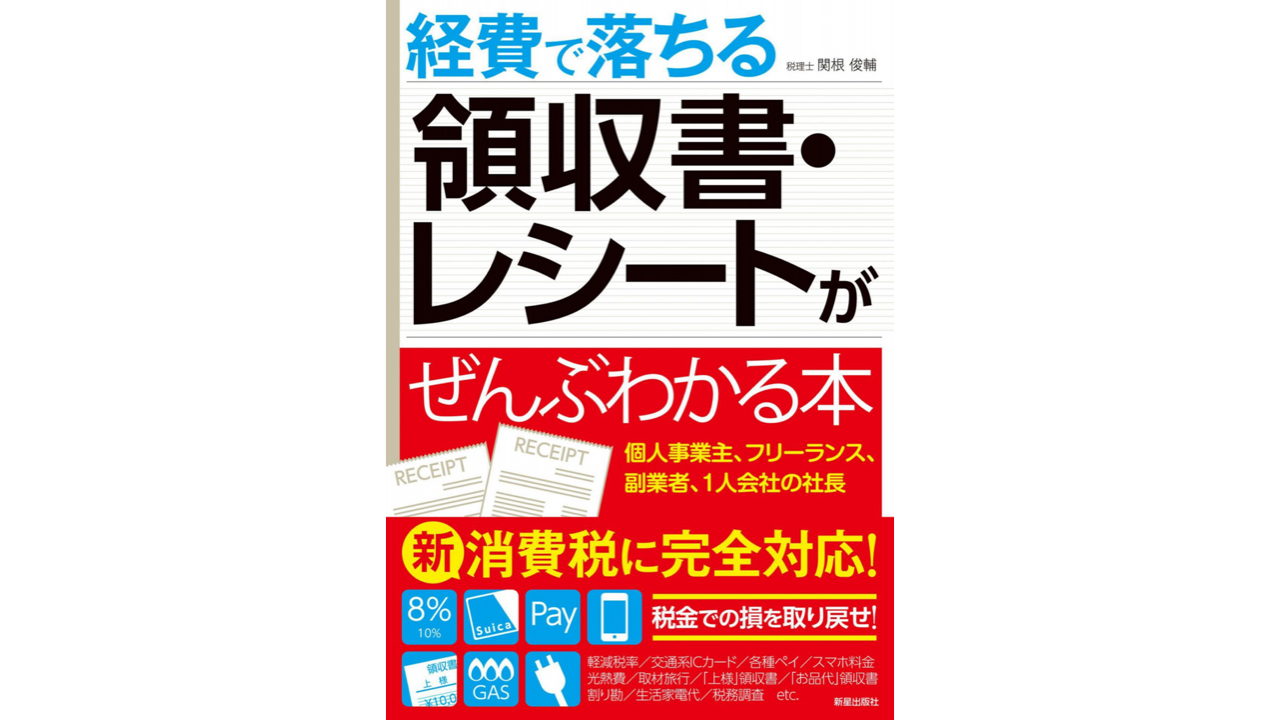
サマリー&レビュー
内容
経費で落とせる支出の種類、経費で落とす際の注意事項を中心に、個人的に何らかの所得がある人が確定申告の際に経費絡みで注意するべき事項がまとめられている。
経費で落とせる支出の種類
- 会議費と接待交際費を適切に分ける
- 自宅兼事務所の家賃代を家事按分で落とす
経費で落とす際の注意事項
- 税務署は経費のバランスをチェックする
- 支出の「ストーリー(事業活動で必要だったという経緯)」を残す
対象者
- 給与収入以外の所得がある人
- 何が経費にでき、どのように申告すべきかがよくわかっていない人
難易度
- 平易な言葉と内容であるため、前提知識がなくても読み通せるとは思う
しかし簿記の知識があった方が、本書への理解はより深まる
評価
★★★★★(5/5)
- 個人的な所得がある人が気にするべき(気になる)事項がわかりやすくまとめられている
- 経費絡みの知識が浅い人にはオススメの入門書
経費と証憑
経費で落とせるかどうか
業務上の経費か、またどこまでが業務上の費用か、がポイント。その支出に「ストーリー(事業活動で必要だったという経緯)」があるか、またそのストーリーを残せるか(あとで説明できるか)にかかっている。
税務署がチェックするポイント
経費のバランスがチェックされる。確定申告で提出された数字は税務署ですべて電子データ化されており、「業種別の接待交際費の平均値」などが容易に集計できる。「接待交際費や雑費の割合が平均よりも異常に高い」などは不正な計上が疑われ、税務調査の対象となりやすい。飲食費を何でも接待交際費に入れたり、わからないものを何でも雑費に入れたりして、経費のバランスをおかしくしないように注意。 また、申告した人がどうやって暮らしているのかもイメージしている。所得ゼロだと「この人はどうやって生活しているのだろう」と違和感を持ち、話を聞いてみたくなる。
任意調査の概要
個人事業には「任意調査」が行われる。脱税の疑いがなくても毎年ランダムに抽出されて調査が入る。事前に税務署から調査に来る旨の連絡が入るが、調査を拒んだり質問に答えないことは許されない。調査の対象になったら丁寧に正確な情報を開示する。 保存しておいた資料が税務調査で役立つ。領収書は当然として、自分の足取りを示すスケジュール帳や日記・日誌、ボツになった企画書など(=ストーリー)が売上や経費の証明になる。交通費には交通費精算書が有効。 説明が十分でないと申告の承認が取り消され、「推計課税(税務署が勝手に推計)」される。領収書等の保存期間は白色で5年、青色で7年とされている。
証憑
領収書としての要件は「発行者の氏名、年月日、取引内容、金額、受取人の氏名」が記載されていること。宛名なしの領収書でも金額が少額であれば慣習的に認められている。支払い方法に応じて下記のような証憑書類が認めらている。
| 支払い方法 | 証憑書類 |
|---|---|
| 現金払い | 領収書、レシート |
| 振込払い | 納品書、請求書 |
個人事業主や1人社長でも、経費の支払い専用のカードを用意しておくとよい。帳簿付けがラクになり、経費の計上漏れも防げる。ただしクレジットカードの利用明細は領収の代わりとならないため注意。
領収書が出ない場合の証憑
領収書が出ない場合(交通費、冠婚葬祭、自販機等)、出金伝票などに記録する。また、支出の内容(5W1H)がわかるストーリーも残しておく。自動引落の場合、通帳のコピーが領収書の代わりとして認められる場合がある。
| 支出 | 通帳代替可否 | 補足 |
|---|---|---|
| 水道代 | ◯ | |
| 電気代 | △ | ガス代は分ける |
| ガス代 | △ | 電気代は分ける |
| ネット | △ | 電話代は分ける |
| 電話代 | ☓ | ネットは分ける |
| スマホ | ☓ | お財布ケータイやゲームの課金は除く |
軽減税率
軽減税率の導入により、税率ごとの合計金額が新たな記載事項として加わった。内訳が正確に記載された領収書はもらいづらくなるため(手間なので)、そのあたりを自動で記載してくれる点でレシートは優れいている。
勘定科目
勘定科目の一覧
| 勘定科目 | 科目内容 |
|---|---|
| 支払手数料 | マンションの修繕積立金・管理費・共益費、引っ越し代 |
| 前払い費 | マンションの更新料・火災保険料 |
| 会議費 | 会議で出すお茶・食事代、喫茶店/レストランのお茶・食事代 |
| 外注費 | ホームページ作成費 |
| 旅費交通費 | タクシー、電車(新幹線・グリーン車・指定席)、飛行機(ビジネス・ファースト)、高速料金、宿代(高級旅館)、帰省代(ただし帰省先で仕事がある場合) |
| 接待交際費 | 取引先への接待(キャバクラ・スナック)、接待後の運転代行料、取引先へのプレゼント |
| 研究費/試験研究費 | 販売に至らなかった新製品の開発費、ボツになった企画の取材費、映画やコンサートの入場料(映画評論家や音楽評論家) |
| 教育研修費 | 英会話レッスンの受講料・本・CD、資格受験料 |
| 新聞図書費 | 書籍、DVD、新聞、雑誌、統計資料、地図 |
| 事務用消耗品 | コピー用紙、ペン、ノート |
| 消耗品費 | 仕事机、イス、キャビネット、パソコン、観葉植物、携帯音楽プレーヤー、作業着、掃除機、洗濯機、冷蔵庫(すべて10万円未満に限る) |
| 通信費 | インターネット、電話代、クラウドサービス |
| 保険料 | 空港で加入した海外保険 |
勘定科目の補足
全般
- 創設費と開業費は経費ではなく繰越資産という資産になる (いつでも何回かに分けて償却してよい)
- 借入金の返済は利息のみ経費になる
- マイルやポイントを利用して購入した場合、その分は経費で落とせなくなる
- 意図的に領収書を分割して10万円以下にしようとするのは脱税になる
- 白紙の領収書に自分で記載するのは税法違反になる(必ずお店の人に書いてもらう)
会議費
打ち合わせの飲食は「会議費」の勘定科目をつくり、本来の接待交際費とは分けるのがオススメ。飲食代を会議費で落とすには、以下の情報を残しておく必要がある。
- 飲食のあった年月日
- 相手の名前・関係・人数
- 店の名前と住所
- 飲食費の内容
一人でコーヒーショップに行った場合、休憩しているのか仕事をしているのかわからないため、経費として認められない。
旅費交通費
税務署は飛行機のクラス(ビジネス・ファースト)など、「贅沢かどうか」には関与してこない。交通系ICカードの精算方法は2種類ある。
| 名称 | 方法 |
|---|---|
| 厳密 | チャージしたタイミングでは「仮払金」とし、交通費として使ったタイミングで「交通費」に振り返る |
| 簡便 | 「交通費明細書」を作成し、使った交通費を明細として残す。そのうえでチャージしたタイミングで「交通費」として計上 |
簡便法の注意点
- プライベートと業務用のカードは別にする
- 交通費以外に使用しない(交通系ICカードで支払いたいならカードを分ける)
- 高額の残高が残った状態で期末を過ぎ、そのまま申告すると経費の過大計上になる
消耗品費
作業着や安全靴などの明確に業務用とわかる服や靴は経費で落とせるが、スーツや靴などのプライベートとの区別が難しい服や靴は経費では落とせない。また、自転車や車の購入も経費で落とせるが、趣味性の高いものは不可。
福利厚生費
個人事業主自身やその専従者、一人社長には福利厚生費が認められていない。
家事按分
家事分を除外して事業の経費だけを計上する帳簿上の手続きを「家事按分」という。自宅兼事務所の家賃、電気ガス、水道、光熱費、固定電話やインターネット回線、スマホ代などが家事按分により経費として含められる。 家事分を含む全額を経費として帳簿に一旦記録し、合理的根拠に基づいた割合で申告を行う。面積や時間など、数字で表せる客観的基準を見つけ、自分のケース(=ストーリー)にあてはめる。 自宅兼事務所の家事按分は、床面積を基準とするのが適切。例えば自宅の床面積の3分の1を事務所として使っていたら、3分の1を経費(地代家賃)とし、残りの3分の2は家事分として除外する。
個人事業と会社の経費の違い
1人社長の給与は一定の条件を満たせばすべて経費にできるため、その点では会社の経費の方がトクといえる。
| 区分 | 一般の経費 | 家事関連費 | 事業主の給与 |
|---|---|---|---|
| 個人事業 | 違いなし | 家事按分できる | 経費で落とせない |
| 会社 | 違いなし | 全部経費か経費でないか | 一定の条件で全部経費 |
副業
副業の確定申告は、「雑所得」か「事業所得」のどちらかで行う。事業所得であれば損益通算(所得が赤字になった場合に他の10種類の所得からその赤字額が差し引ける)できるが、雑所得だと損益通算できない。損益通算可能な所得は、「不動産所得」「事業所得」「譲渡所得」「山林所得」のみ。
事業所得の条件
- 自分の考えで行い、リスクも取っている
- 無償ではなく、営利を追求している
- 繰り返し、継続して行っている
- 常識的に見て、事業として認められている
FXや暗号資産取引
「雑所得」扱いであり、他の所得と損益通算できない。取引所に払った手数料や取引のために使用しているパソコン、スマホなどの機器代金、インターネット料金、新聞図書代などは経費として落とせる。ただし家事按分の考慮は必要。
ネットオークション・フリマ
売上があった場合、出品物の購入代金は仕入れとして落とせる。発送の宅配便代なども経費になる。
売上規模と消費税
1000万円以下では免税となるため、「売上は990万円」などと嘘をつく事業者が多く、これは脱税行為になる。
| 売上高 | 消費税 |
|---|---|
| 1000万円以下 | 納税義務なし(免税事業者) |
| 5000万円以下 | 簡易課税(預かった消費税額に一定の率を掛けて支払った消費税額をみなし計算) |
| 5000万円以上 | 原則課税 |
その他
青色申告のメリット
- 青色申告特別控除(簡易簿記なら10万円、複式簿記なら65万円)
- 純損失の繰越控除(赤字になった年の損失を全額、翌年以降に繰り越せる)
- 青色事業専業者控除(事業を手伝う家族に支払う給与を全額経費にできる)
- 少額減価償却資産の特例(30万円未満のものは、その年の経費として一括計上できる)
ただし、経費の発生は「現金主義」ではなく「発生主義」で記帳しなければならず、白色よりも管理に厳格性が求められる。
適格請求書発行事業者
適格請求書発行事業者とは、売上が1000万円以上の課税事業者のうちで、税務署に申請書を出して「私は課税事業者です」という証明書をもらった事業者のこと。この証明書をもった事業者しか適格請求書を発行できない。 適格請求書発行事業者でない事業者が発行した請求書に消費税額が書かれていたとしても、それを「支払った消費税額」として加算することはできない。つまり、適格請求書発行事業者でない事業者と取引すると納める消費税額が増えてしまう。 免税事業者も課税事業者になることで適格請求書発行事業者になることができるが、免除されていた消費税の申告・納税を行わなければならなくなってしまう。取引相手が一般消費者か免税事業者であれば、相手は適格請求書の保存など行わない(消費税を収めない)ので、適格請求書発行者になる必要はない。逆に、相手が1000万円以上の事業者なのであれば、適格請求書発行事業者になることが望ましくなる。
奥さんの給料
| パターン | 給料 |
|---|---|
| 個人事業&白色申告 | 事業専従者控除(所得が減り、税金が減る) |
| 個人事業&青色申告 | 青色事業専従者給与(実質的に経費) |
| 会社&従業員 | 従業員給与(経費) |
| 会社&役員 | 役員報酬(経費) |