ビジネス会計検定試験 公式テキスト 3級
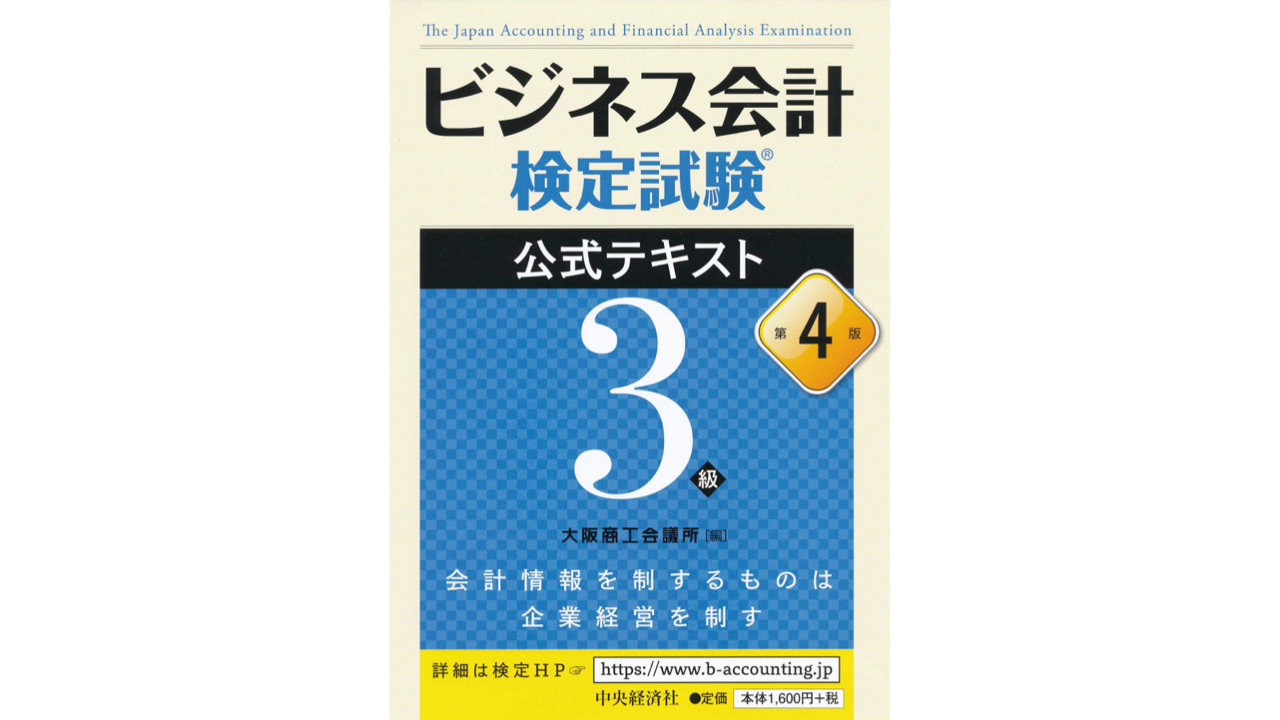
サマリー&レビュー
内容
財務三表と財務諸表分析の初歩的な説明からなる。財務諸表分析の主要な内容は下記となる。
- 安全性の分析(流動比率、手元流動性、自己資本比率等)
- 収益性の分析(ROI、ROA、ROE)
- 1株当り分析(EPS、PER、PBR等)
対象者
- 財務諸表分析の初歩を学びたい人
- 簿記は知っているが、その後どのように活用されるのか知らない人
難易度
- 財務三表の説明が、この本の内容だけでは腑に落ちないところがあるかもしれない
簿記学習者であれば、財務三表の説明部分もしっかりと理解できる
評価
★★★★☆(4/5)
- 自分の投資判断の糧とするために学習したが、「それ、知っていて投資の何の役に立つの?」的な”試験のための知識”も多かったため星を1つ原点
- それでも、企業の決算報告や四季報なので頻出するキーワードを、しっかりと初歩から包括的に学び直せたのは良かった
財務諸表
貸借対照表
貸借対照表は、資金の調達源泉とその運用形態を明らかにする。
貸借対照表の構成要素
- 資産
経済的利益をもたらすと期待されるもの。貨幣額で示すことができないものは資産として扱われない - 取得減価
資産の取得のために支出した金額のこと。時が経過するにつれて資産価額が実態からかけ離れてしまう - 時価
期末時点での資産の評価額のこと - 減価
価値の下落のこと - 自己株式
買い戻した自社株式のこと。自己株式の取得は、株主に対する会社財産の払い戻しと考えられる
損益計算書
損益計算書は、利益をその性質によって区分して表示し、利益獲得のプロセス(過程)を明らかにする。多額の借金を抱えているために支払利息の負担が大きく、経常損失になることもあれば、天災によって多額の特別損失が生じ、最終的に当期純損失となることもある。
損益計算書の構成要素
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書は、貸借対照表に記載されるキャッシュの1年間の増減、すなわち前年度末のキャッシュと当年度末のキャッシュの増減の原因を説明する。一方、損益計算書は、配当金の支払いなどによる増減がない場合、前年度末の貸借対照表の利益余剰金と当年度末の貸借貸借対照表の利益余剰金の増減の原因を説明する。
企業活動
企業が事業活動を行うためには、手元としての資金が必要。企業はまず資金を使ってさまざまな準備をし、その後に営業活動を通じて資金を回収する。この順序を理解することが重要。企業の活動は、資金の循環(資金の支払いと回収)として捉えることができる。資金は企業経営にとっての血液にたとえられる。
- 営業活動
企業の本業(売上高、売上原価、販売費及び一般管理費) - 投資活動
設備投資や余剰資金の運用 - 税務活動
資金調達や借入金返済
算出方法
キャッシュ・フローとは、資金の増加(キャッシュ・インフロー)と資金の減少(キャッシュ・アウトフロー)を意味する。
\[\begin{align} キャッシュの期末残高 &= キャッシュの期首残高 + キャッシュの期中増減額 \\\\ キャッシュの期中増減額 &= ( 営業活動からの収入 - 営業活動への支出 ) \\\\ &+ ( 投資活動からの収入 - 投資活動への支出 ) \\\\ &+ ( 財務活動からの収入 - 財務活動への支出 ) \end{align}\]営業活動によるキャッシュ・フロー の算出
2種類の算出法がある。基本的には間接法が用いられる。
- 直接法
キャッシュによる取引を記録しておき、それらを足し合わせる(従来の簿記のみでは対応不可) - 間接法
利益からキャッシュの取引とは関係のない項目を差し引く(従来の簿記のみで対応可能)
循環パターン
| 営業 | 投資 | 財務 | 解釈 |
|---|---|---|---|
| + | + | + | 事業の転換を図っている企業にみられる |
| + | + | - | 負債を減らし財務体質の改善に取り組んでいる |
| + | - | + | 健全な資金繰りであり積極的な投資を行っている |
| + | - | - | 健全な資金繰り |
| - | + | + | 資金繰りの観点から注意が必要 |
| - | + | - | 銀行からの借入れができなくなっている可能性がある。この状況が続くと資金繰りが厳しくなる |
| - | - | + | この状況が続くと資金繰りが厳しくなる。将来、投資活動の成果としてキャッシュ・インフローを得られるかどうかが分かれ目 |
| - | - | - | 過去に蓄積したキャッシュで投資活動を行い、かつ借入金の返済も行っている。この状況が続くと資金繰りが厳しくなる。将来、投資活動の成果としてキャッシュ・インフローを得られるかどうかが分かれ目 |
キャッシュ・フローの解釈
- 投資活動によるキャッシュ・フロー
将来の利益やキャッシュ・フローを生み出すための投資は十分か、資産売却の内容や価額は適切か - 財務活動によるキャッシュ・フロー
営業活動と投資活動によって生じた資金の過不足がどのように調整されたか
フリー・キャッシュ・フロー
フリー・キャッシュ・フローは、「投資活動を営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内で行えば、資金の状態が安定する」という考え方を反映した指標。企業にとって投資活動は将来の存続・成長を支える重要な活動である。時として大きな投資も必要であり、フリー・キャッシュ・フローの値は常にプラスでなければならないという考えは適当ではない。
\[フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー\]財務諸表分析
分析の種類
2種類の分析方法がある。
- 比率分析
ある数値を、他の同じ単位の数値で割ることによる分析。結果は無単位になる - 実数分析
結果に単位があり、1株当たり分析などがある
基準値の種類
分析結果はそれ単体では意味がなく、何らかの値と比べることで意味を見いだせる。業界や会社規模に応じて特性が異なることから、相対基準が基本的に用いられる。
- 絶対基準
固定的な特定の値を判断基準とする - 相対基準
何らかの比較対象値を判断基準とする
構成の分析
- 百分比貸借対照表
貸借対照表の各項目の金額を資産合計で割り、百分率で表現するもの。これにより貸借対照表の構成が把握できる - 百分比損益計算書
損益計算書の各項目の金額を売上高の金額で割って百分比で表現したもの。これにより損益計算書の構成が把握できる
成長性の分析
- 対前年度比率
分析対象年度の数値を前年度の数値で割った値をパーセントで表したもの。図表に入っていない項目間の伸びの均等性や不均等性もみることもできる - 伸び率
分析対象年度の数値から前年度の数値を差し引いた金額を前年度の金額で割ったもの。前年度数値がマイナスの場合には前年度比率と伸び率は分析対象外とするのがよい - 対基準年度比率
特定の期の数値を基準として、他の期の数値をパーセントに置き換えるもの。重要な留意点として「基準年度をどの年度にするか」という問題がある。一般的には分析対象の初年度を基準年度とするが、初年度が異常な状態と考えられる場合には、正常と考えられる他の年度を基準年度にする
安全性の分析
企業の支払い能力や財務的な安定性を判定する。
自己資本比率の企業規模に応じた値
- 上場企業
資金を資本市場から調達できる上場会社の自己資本比率は40%台 - 中小企業
借入れに依存する中小企業の自己資本比率は10%-20%台
適切な手元流動性
現金を持っていることは、各種の投資や決済に対応できるという利点はある。しかし、資産には負債や純資産という源泉があるため、投資計画や資金計画で必要のない現金は、利益を生まないのにコストがかかることになる。負債には利息がかかり、純資産には出資者から期待収益(出資の見返りとしての配当や値上がり益)を期待される。 無用な支払利息を伴う遊休資産は返済に充てるのが望ましく、期待収益に見合う稼ぎがない資産の保有も望ましいことではない。したがって、資金不足に陥らないための資金保有は絶対に必要であるものの、指標は必ずしも大きければ大きいほど良いというわけではない。
収益性の分析
企業活動の基本目的は、資本・資金を投下し、投下した資本・資金を超える利益をあげることにある。
- 売上高利益率
売上高に対して利幅が大きい事業活動を行っているか否か - 資本回転率
投下資本がどれだけ効率的に売上高を生み出したか
(投下資本が何回回転して売上高を稼いだか)
ROI/ROA 補足
資本利益率や資産利益率は概念的な指標であり、ROIやROAは一般的に総資本経常利益率を指す。分母の負債純資産合計には、前期末と当期末の平均値を用いることもある。 日本では、大きめの先行投資を行い、大量生産型の体制を築き、シェアを獲得することによって優位性を保つ傾向があったことから、総資本回転率は1回付近と低めの値となっている。先端技術やICTに巨額の投資をする国々では、日本以上に回転率が低下するようになってきている。
ROE 補足
ROEは、株主の出資に対する収益性を判断するための指標である。 財務レバレッジは、自己資本比率の逆数にあたる。財務レバレッジを高めるということは、自己資本比率を低下させることにほかならない。支払利息を越える利益を稼ぐ能力のない会社は、増大した支払利息が業績を悪化させ、倒産リスクが高まりかねなくなる。
1株当たり分析
1株当たり分析はファンダメンタル分析と呼ばれる。
PER 補足
株価収益率は株式投資者の利益に対する先読みを反映すると言われる。平均的な株価収益率が将来にわたって20倍であると想定すると、現在(株価:1000円、1株利益:100円、株価収益率:10倍)の株価は、2000円近辺でもよいはずとなる。
BPS 補足
資産と負債の評価観は、解散価値と呼ばれる。実際の市場評価は、解散価値ではなく、企業が継続することを前提とした継続価値で評価される。 資産にはオフバランス(貸借対照表に載っていない)の隠れた脆弱性がある。貸借対照表に計上されている金額よりも価値がないと見込まれれば、純資産は計上額よりも低いと考えられ、株価が1株純資産を下回ることがある。また逆に、資産にオフバランスの財産価値が認められれば、上回ることもある。
1人当たり分析
生産性とは、ヒト・モノ・カネの投入量に対する生産量の割合のこと。
\[従業員一人当たり売上高 = \frac{売上高}{従業員数}\]この指標は、労働時間当たりの労働効率が低くても、労働時間が長いために1人当たり指標が高くなるという問題を内在している。