スモールビジネスの教科書
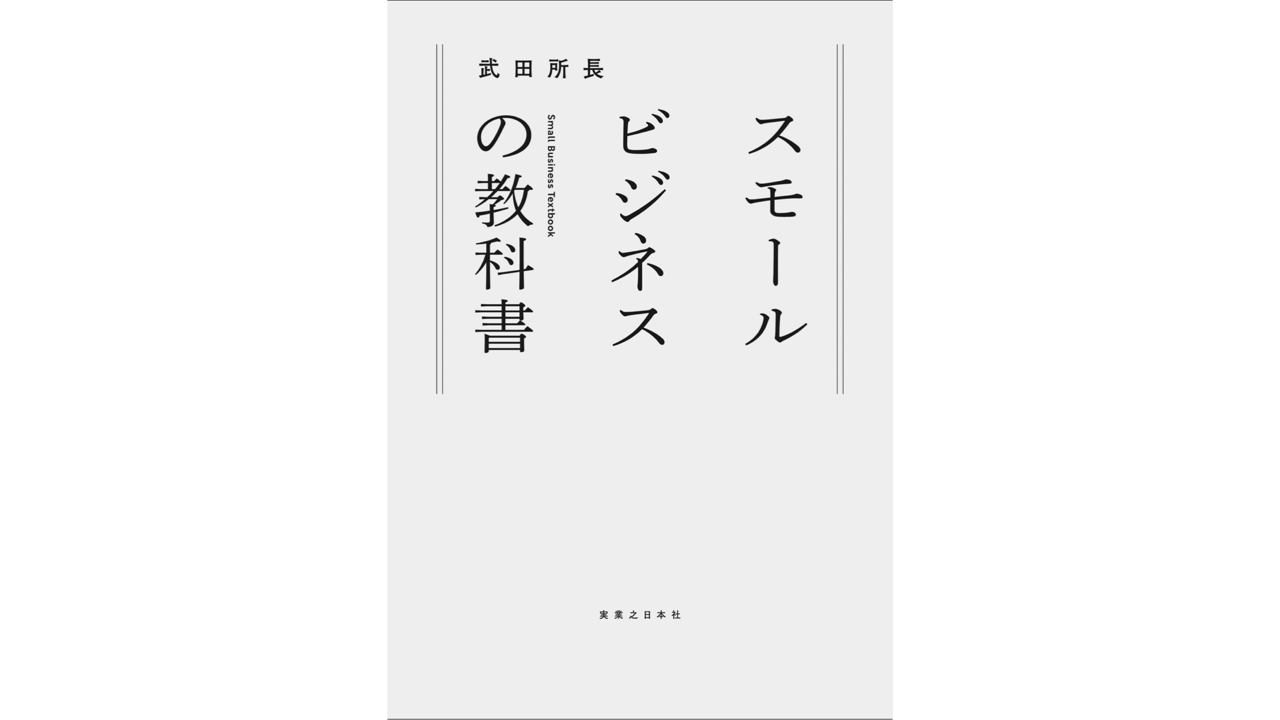
スモールビジネスとは
安定着実を重視し、自己資本で運営する。 既に成立しているビジネスに、自分が対象とする顧客セグメントのニーズを反映させ、マイナーチェンジする。
スタートアップとの違い
スモールビジネスで「イノベーション」は必要ない。社会や産業構造の変革も目指さない。
| スタートアップ | スモールビジネス |
|---|---|
| 株で儲ける | 営業利益で儲ける |
| 危険度を許容する | 危険度を許容しない |
| 外部資本を前提とする | 自己資本を前提とする |
| スケーラビリティ追求 | ステイスモール |
ビジネスモデル
実はビジネスモデルにはあまり変化の余地がない。ビジネスモデルに独自性を与え、競争力をもたらそうという発想は失敗に終わる事が多い。 重要なのは対象とする顧客セグメントとコンテンツである。マイナーチェンジコピー品を作れないだろうか?と考えてほしい。
スモールビジネスに向くビジネス
基本条件1 課題自体に多くの人が気付きづらい
存在すら知られていない課題に取り組む。仕事を通じて「少人数しか持たない強いニーズ」を発見したなら、それは宝の可能性がある。 多くの目に触れるような気付かれやすい課題は、必然的に参入者が過剰になる。
基本条件2 自分の趣味・経験があるからこそ出来ること
優位性を担保するのは自分の能力である。
基本条件3 属人性がある
一般的にはスケールの妨げとなるためビジネスの敵とされる属人性もスモールビジネスでは味方である。
基本条件4 称賛されない
褒められたところで全く儲からない。
基本条件5 既に類似サービスにお金を払っている市場が存在する
既に金が支払われており、サービス提供者も儲かっている状態の市場に参入し、その金を少しかすめ取る方法を考えて実行する。 エクセレント・カンパニーのゴミ拾いをする。
スモールビジネスに向いていない人
信頼を大切にしない
技術などで決定的な差別化手段を持たないスモールビジネスでは、人とのつながりは最重要な差別化要素になる。
リスク選好性があまりに低い
細かい投資を繰り返すことで安定する。数十万円の投資も許容出来ないほどリスク選好性が低いことは致命的である。 部分的にその要望を叶えるサービスを提供したとすると、無限のアップセル・クロスセル連鎖が始まる。 これがスモールビジネスに安定性を与える。
バーニングニーズ
バーニングニーズとは、「これさえ出来れば他はよい」というニーズの王様のこと。バーニングニーズを参入の着火点にする。 徐々に炭に火を移すようにサービスを整備し、「不愉快さ」を除去する。
注目されていない儲かる渋い課題
スモールビジネスでは、他人があまり知らないこと、関心を持たなそうなことに取り組む。渋い課題を見つけることが成功の第一歩である。
誰も知らない山を注意深く登る
不動産業界や医療業界では、部分的に見える情報から無策な参入を行い、失敗するケースが大量に見られる。 一見非効率に見えるローテクなオペレーションが実は効率的であり、クラウドサービスなどが役に立たないのである。 どの業界にも賢い人はいて、効率化の動きは常に進められている。なされていないとすれば、なされていない理由がある。 少し調べれば、自分と同じ失敗をした例などは大量に出てくる。
顧客の課題を考えるのは無駄
売上目標が20億円程度であれば、まず得意な取り組みはしないほうが安全。 顧客の課題に注目し、ゼロベースで解決手段を模索するアプローチは、スモールビジネスで最も推奨されないアプローチ。
課題を啓蒙しない
「顧客自信は課題を認識していないが、自分は課題だと思っている」という課題に取り組むには、啓蒙プロセスを含むため辞めたほうがよい。 重要なのは、あなたではなく「顧客自信が金を使うほど重要なニーズ」だと思っているか否かである。 言動やアンケートでは信頼に足らない。本音の把握には行動以外見る必要はない。
課題解決と欲望実現
- 課題解決型 市場が成熟しており、顧客が課題を十分認識している
- 欲望実現型 新規性の高い市場を狙う
人間は欲望に弱い
顧客の実現したい姿に向けて、ボトルネックを1つ1つ除去していけば、複数のサービスを連鎖的に作ることができる。 「コストが減る」と「売上が伸びる」という2つの誘惑を比較すると、欲望(売上が伸びる)のほうが誘惑が強い。
顧客セグメント
購買決定要因でカテゴライズする。年齢のように、すぐに思いつくが適切にニーズを区分できないカテゴライズは、ターゲットとする集団を有効に特定できていない。 マーケティングで活用できない軸は単なる遊びであり、実務的な意味を持たない。
顧客を理解する
商品を買う、というのは極めて心理的な現象。論理的に考える力が強い人でもこの商売の勘所がずれている人は多くいる。 対象セグメントの感情と自分を一体化させる。
水先案内人
飛び地に参入する際は、業界の水先案内人であるパートナーとともにビジネスを作る。パートナーに求めるのは業界の深いナレッジおよびコネクションである。
狙うセグメント
業界を正しく選べば何をやっても成功する。新しい顧客セグメントは、大量の事業機会を生む。
- 顧客セグメント自体が成長している
- 投資意欲が旺盛
- 利益率が定常的に高い
- 新規参入の人気がない(競合が少ない)
狙う予算
誰のどの予算をもぎ取るのか、これは根源的な問いである。 狙うべきは、プレッシャーが弱い予算。プレッシャーの強さは、自分が提供するサービスの代替性、購買決定プロセス、顧客セグメントの性格に大きく左右される。 対象顧客の意思決定プロセスは、極めて重要な情報。
避けるセグメント
「金払いが悪い」と「要求が多い」が両立している顧客は多い。「よかったら払うからさ」と言って安値での提供を求める顧客は経験上、悪い顧客である。
コンテンツとチャネル
コンテンツ
顧客は「自分・自社が理解できる普通に良いもの」が欲しい。 「それって他社と何が違うの?」という質問に対し、「あまり変わらないけど、安くて品質は良い。顧客や代理店に誠実に対応しているからそこそこ売れる」を目指す。
マイナーチェンジの定番
- 対象セグメントを絞りサービスの競争力を局所的に高める
- 提供サービス・機能を絞り価格を下げる
組織の病(ひたすら多機能化)にかかった重病人を小突くことは容易い - マーケティング軽視業界でマーケティングを最適化する
マイナー製品ではチャネル別のマーケティングが最適化されておらず、マーケティングのみで勝てるビジネスが数多く存在する
チャネル
偉大なチャネルに愛されるスモールビジネスは盤石である。 金を使えばアポが取れる・集客出来るという持続的に機能するチャネルを数あるオプションの中から発見し、最適化をしなければ事業が軌道に乗ったとは言えない。 チャネル・プロダクト・フィットを目指す。
代理店
法人向けビジネスにおいて代理店というチャネルは偉大。代理店はアポをトスアップするアポゲッターで、自分はクローザーであるべき。 日本の事業会社に対してはほぼ例外なく、電通や博報堂、ソフトバンク、CTC、アクセンチュア、大手広告代理店、SIer、コンサルティングなどが入り込み、強い影響力を持っている。
事業創出のステップとポイント
以下のステップで事業創出に望む。
- 模倣する会社の選定
- 提案書の作成と提案
- MVPの作成と精錬
- 市場投入
- 障壁創出と前進
模倣する会社の選定
エクセレント・カンパニーを徹底的に調査する。特定領域で儲かっている会社が核としている戦略を見れば、その領域での儲け方がわかる。 事業領域内の成功要因をコピーし、その会社のミニバージョンを作成する。
IR
業界内の上場企業のIR資料をすべて見る。トレンドをキャッチするために、新規上場企業の情報には目を通す。
ポイント
- 何がいくらで誰に何故売れているのか
- コスト構造(何にコストがかかっているのか)の分析
そのビジネスのコピーに何が必要になるか把握できる
投資情報
どこかに投資がなされているのであれば、そこには何らかの根拠が存在する。 ある程度の調達がなされたとしても、スタートアップの成功率は高くないため、必ずしも儲かるチャンスがあると保証するものではない。
提案書の作成と提案
顧客向け提案書の作成から調査を始める。
提案書の構成
- 顧客の課題とそれが深刻である理由
- 顧客が課題解決のために現在購入している商品・サービス
購買決定要因の把握を間違えると、あとからの軌道修正が難しくなる。 - 顧客の課題が解決されていない理由(何故先行他者はその課題を解決しないのか、出来ないのか)
まともに課題解決ができるプレイヤーにとって、それは好機ではない。 - あなたが提供する商品・サービス
普通のものを安定・安価提供することに務める。コンセプトの差別化に逃れない。 - 何故あなたは未解決の課題を解決出来ると主張できるのか
過去実績がさらに実績作りの機会を呼び、特定の実績が雪だるま式に膨らんでいく。 - 売値は競合商品と比較して妥当か
提案書の提案
本格的なプロダクトを作る前に、顧客へ提案書を持っていく。まずは、提案書の刺さり具合を確認する。 ビジネスの2大論点である、「使われるのか」と「金は払われるのか」に対して論理のみで高い確度で答えを出す方法は残念ながらない。
顧客とのコネクション
可能な限りカジュアルな議論も出来る顧客・協業相手を増やしておくことは重要。 試験的な提案を顧客・協業相手にぶつけていく。 相手にその提案内容が刺されば、実現するためにはこうして欲しい、ここに注意すべきだという貴重なアドバイスを得ることが出来る。
MVPの作成と精錬
バーニングニーズを解消する機能のみを開発する。 ビジネス初心者は顧客の要望を詰め込みたくなってしまうが、全てを受け入れるとリソースが限られているスモールビジネスはすぐに納品不可の状態に陥ってしまう。
他社が使えないサプライヤーの活用
調達に注意したビジネスは安定して勝てる。 ビジネスモデルやサービス内容に全く新しさはなく、顧客からは普通のサービスに見えても、サプライヤー選定をうまくすると勝てる。 原価の面で優位だからだ。
新規参入者であり、他者に利用されいないサプライヤーを早期に使用するのは定番のパターン。 サプライヤーは新規参入のために価格は割り引き、サービスも過剰気味に行う。 信頼性を重視する大手との取引につなげるために、実績を蓄え値上げ機会をうかがっている。
社員教育
社員教育は余裕ある大手企業のみならず、スモールビジネスにとっても生命線である。 良質な人材が市場価格月額100万円で取引されていたとしても、給料30万円と会社の監督コスト10万円で同等の価値が実現出来るとしたらどうだろうか。
市場投入
最初はとにかく売れることを重視すべき。事業開始を華々しくSNSでアナウンス出来るようなものではないほうが望ましい。
自分が作ったサービスに継続的に顧客が供給される安定的なチャネルを見つけ出すことが、この段階では重要。 細かい試作と効果測定を早いサイクルで繰り返し、常にビジネスが成立する顧客獲得コストで新規顧客を流入させ続ける。
障壁創出と前進
優位性を築くことでビジネスは持続可能な状態になる。障壁はビジネスを運用する中で作り出してく。
また、前進し続けることで安定着実なスモールビジネスを継続することができる。 常に新規顧客を獲得し続けると同時に、顧客が持っている要望に沿って、階段を登るように多数のサービスを作り続けていく。
事業戦略
誰かが儲かっている、そこには金を払っている顧客がいる。サービスの提供者は何らかの工夫により、そこで原価との差分であるマージンを得ている。 この事実こそ、ビジネス検討の出発点として何よりも重視すべき。
売れる自信がない状態で実行してしまうと、そのあとに長く苦戦を強いられることになる。儲かる自信がない戦略は躊躇なく捨てる。
戦略の妥当性チェック
- 現在はAを解決するために何をしているか
- 何故その方法を取っているのか
- Aを解決する方法は1つだけではない
- 外部の会社からサービスを購入している場合、何故その会社に決定したのか。どこと何を比較したか
- どのような意思決定プロセスか
- 特に法人相手にビジネスを行う場合は誰がどこで情報収集をし、どう稟議を起案したかを聞く
- どこのチャネルから購入したか。そのチャネルからは他にどのようなサービスを買っているのか
- 代理店なのか、直販なのか、何故そのチャネルにしたのか
- 導入後の効果はどうか。十分にAを理解出来たのか、もしくは部分的な解決に留まっており不満があるのか
- 現在持っている不満は何か
- これを聞く際には自分が持っている仮説をぶつける
スケーラビリティは無視する
十分に他社が努力し実証したビジネスモデルにコンテンツを付与し、美味しい顧客セグメントに当てはめるだけ。 スモールビジネスは市場規模と成長性に目をつむることで、事業機会の発見を容易にするというアプローチを取る。
スモールビジネスの強み
大企業もスタートアップも小さな市場を積極的に選ぶことは出来ない。 スモールビジネスでは間接費を除去することができる。 そのため大手企業であれば赤字案件と呼ぶような案件でも、積極的に獲得する戦力を取れる。
疑わしい「先行優位性」
ビジネスの計画に「先行優位性」が登場した際には疑ったほうがよい。 一度導入してしまったら他社製品が使いづらいという特徴を持った製品は、先行優位性が機能する。
フレームワークでの整理は成功を保証しない
何があなたのスモールビジネスの成功を保証してくれるのだろうか。それは成功しているビジネスの亜種から始めることである。 論理というのは、現実世界を戦う武器として非常に頼りないことを重々承知して欲しい。 目の前で儲かるものをつないでいく。 儲かるビジネスが目の前に登場した際に飛びつけるかが、まずは勝負なのだ。
刺さったフレーズ抜粋
目の前の偶然をビジネスに昇華する
江副氏がそのようなインサイトを持ったのははっきり言って、偶然に東大新聞でアルバイトをしていたからに過ぎない。 目の前にある偶然をどのようにビジネスに昇華していくか。 私は、ビジネスは元来、大上段に振りかぶったテーマよりも、一杯のうどんをお客さんに出す、そしてお客さんがそれを美味しいと感じて喜ぶ、その喜びが世界に伝播していくというところに本質があると考える。 ビジネスとは本来、不確実で、泥臭く、地味で、汚いものなのだ。
その他
やりたいから参入するのではなく、成功するから参入する。成功するものをやりたいと感じるようになる
特殊な技術開発を含まないスモールビジネスにおいて、顧客基盤は長期間あなたに安心感を与えてくれる
儲かっているプレイヤーは最も儲かっている顧客セグメントに注力し、収益性の観点から次点になる顧客セグメントの優先度を下げるため、そこには攻撃の機会が必ず存在する
参入企業数に対して儲かっている割合があまりに少ない領域は危険である
特定の業界に興味を持ったらスモールビジネスを経由し、ビッグビジネスに乗り出しなさい