営業
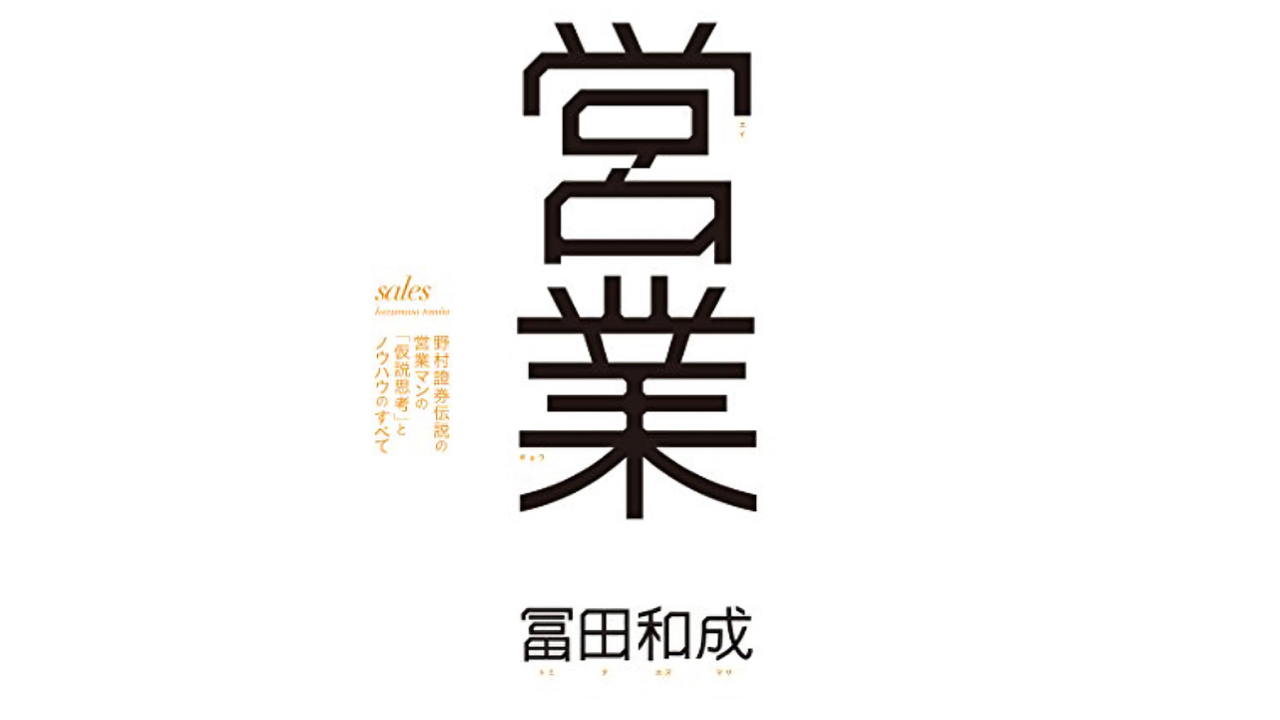
序論
時代は「御用聞き営業」から「仮説営業(顧客に会う前にニーズの仮説を準備する)」へと変化している。 営業としての成長とは、能動的に「型」の数を増やすこと。
「セールス重視」から「マーケティング重視」へ
「顧客をどう説得するか」より、「どの顧客を説得するか」の方がインパクトが大きい。
- 内勤営業(インサイドセールス) … アポ前
- 外勤営業(セールス) … アポ後
仮説営業に必要な力
- 仮説思考力
- 仮説思考とは、課題の原因を推論し、それを検証するマインドセットのこと
- 妄想で終わらせず、実行に移して検証し続けることが重要
- 顧客の課題(ニーズ)の特定で本領を発揮する
- 因数分解力
- できるだけ細かく分解する
- 大きな数値目標は必ず分解する
- 年間売上目標は、月単位などに分解する
- コツ
- プロセスで切る
- 「量 x 質」で切る
- MECEを意識する
- やるべきことが明確になるまで分解を続ける
- 課題を分解しても、解決策を分解してもいい
- 分解できたと思ったら、さらに1段深堀りしてみる
- 確率論的思考法
- 営業は確率の世界
- PDCAを回し続ける力
- PDCAにおける計画(=課題に対する解決策)はすべて仮説
- サイクルを回して仮説が定説になったものが、営業が増やすべき「型」
- PDCAでもっとも難しいことは、PDCAサイクル自体を続けること
- 習慣づけるコツは、同時に多くのPDCAサイクルを回さないことと、大きな課題に取り組まないこと
- ステップ
- ゴールを定量化する(KGIの設定)
- あらゆるPDCAは、たどり着きたいゴールを決めることから始まる
- ポイントは、期日、定量化、具体性
- 定性的な目標であっても、それを数値化し、具体的に把握しやすい状態に置き換える
- 現状とのギャップを洗い出す
- ギャップを埋める課題を考える
- 課題を優先度づけして3つに絞る
- タスクを同時に抱えすぎるとフォーカスポイントが曖昧になって成果が思うように出せなくなる
- 各課題をKPI化する
- KPIは、ゴールに近づくための「サブゴール」
- KPIを達成する解決案を考える
- 解決案を優先度づけする
- ゴールを定量化する(KGIの設定)
マーケティングプロセス
- リスト選定・顧客の絞り込み
- リスト選定にもPDCAが効く
- 仮説を立てたらまずは小さく試す
- 「もっといいリストはないか」と問い続ける
- 最重要顧客のペルソナをひたすら考える
- 「顧客はすでに課題への理解があるか否か」も重要な因子
- リスト選定にもPDCAが効く
- 情報収集とニーズの仮説構築
- ファーストコンタクトで自分のことを「ただの営業」だと思われるのか「使えそうな営業」だと思ってもらえるのかで、 天と地の差が生まれることをもっと意識すべき
- 経営課題の仮説を立てるのは決して簡単なことではない
- 企業の事業モデル、業界の動向等、自分が経営者になったつもりでありとあらゆる情報を持っていないといけない
- アプローチ
- 流れ作業でアプローチしていると思われないか、下心(営業色)を消せるかが勝負
- 営業をかけるなら決済者をダイレクトに攻める
- 受付突破率こそが営業プロセスの最大のボトルネック
- 受付突破の2大パターン
- 自分と相手(経営者や決済者)との関係性を感じてもらう
- 提案と相手のニーズとの関係性を感じてもらう
- 見込み顧客管理
- 見込み顧客管理の目的
- 時間効率の最大化
- 適切なタイミングで機動的に提案しにいける
- 中期・長期の顧客は、自分の手間をかけないで関係性を維持する
- 見込み顧客管理の目的
- 面談
- ニーズ喚起が重要
- 相手の課題の遠からず近からずのところから始めて、いつの間にか本題に入る
流れを切らないことが重要
- 「相手が話したいことで、なおかつ普段話せないこと」を話題に選ぶ
- 孤独な経営者のよき相談相手になれるように努力を続ける
- 信頼
- 人間的信頼 … 感情
- ビジネス的信頼 … 合理
- 人間的信頼関係で大切なこと
- 信頼されないことをしない
- お互いの信頼関係は比例する
- 相手との共通の話題や体験を持つ
- 共通項を探す。共通項が多いほど人間的信頼関係は強くなる
- 相手の価値観に共感する
- 究極系は、その人の哲学や生き様に共感すること
- 信頼されないことをしない
- プレゼン・検討
- あくまでも「相手の課題を解決するためのプレゼン」であるべき
- プレゼンの順番
- Whyの明確化(課題)
- Whatの明確化(ゴール)
- How・When・Whereの明確化(実行策)
- 営業感のある言葉は使わない(相手が急速に冷める)
- 紹介
- 自分からわざわざ「紹介してください」と言わなくても、自分の強みを相手に印象づけることさえできれば、向こうから声がかかることが多い
- 名刺交換のタイミングでは、自分は何ができるのか、何の専門家なのかということを1つや2つに絞って伝える
- 経営者や富裕層のコミュニティでは、基本的に2人紹介したら最低1人は紹介されるというのが暗黙のルール
- 優良顧客でなくても、「優良顧客の人脈を持っている人」なら、時間と手間をかける 業界に影響力を持っているような人をたった1人でも突破できれば、そこから横に広がっていく
- 自分からわざわざ「紹介してください」と言わなくても、自分の強みを相手に印象づけることさえできれば、向こうから声がかかることが多い
その他
成長のための思考と行動
小さなことを積み重ねることが、とんでもないところに行くただひとつの道。 インプットとアウトプットを繰り返す。
分解とは思考を深堀りすること。 深堀りするからこそ、いままで気づかなかった課題が見え、課題が見えるから解決策をひねり出そうとなる。 絶えず問い続ける。
成長に繋がらないことに時間を割かない。 日々の振り返りに時間を割く。
日々の業務が、自分が本当に叶えたいと思っている目標につながっているのだということを絶えず意識することが、継続的な努力のコツ。
強い営業組織
「この目標を達成するためにはどう行動したらよいのか」と全員が考える。 本音を出しやすくする工夫としては、甘いものを持ち寄るなど、少しカジュアルな雰囲気を演出するといい。
ミッションやビジョンをどう社員に定着させればいいのかというと、基本はこれでおかというほどに言い続けて、言い続けて、言い続けること。
部下に「自走力」をつけてもらうことは育成の基本。